
36協定(サブロク協定)とは?意味や手続きをわかりやすく説明します

会社の人事担当者でなくても、36協定という言葉を聞いたことのある方は多いと思います。
ですが、36協定の正確な意味や内容を答えられる方は少ないのではないでしょうか。
36協定は、従業員に残業や休日出勤を命じるために必要となる届出です。
そのため、会社の人事や労務担当者はもちろん、会社の経営者や幹部の方も、当然知っておくべき手続きといえます。
そこで今回は、36協定の基本知識について、わかりやすく簡単に他社事例なども交えながら解説したいと思います。
”「最新の法改正」や「人事トレンド」など、人事・労務担当者必見の資料を配布中!”
→こちらから無料でダウンロードできます
36協定(サブロク協定)とは?正式名称は?

36協定とは、従業員に残業や休日労働を命じる際に必要となる手続きのことで、正式名称を「時間外・休日労働に関する協定届」といいます。
労働者の労働時間については、労働基準法という法律で厳しく制限されており、会社は労働者に対し、残業や休日労働などを命じることができないのが原則です。
しかし、残業や休日労働が全く許されないとなると、会社は繁忙期に対応できず、現実的ではありません。
そこで、会社と労働者との間で労使協定を締結すれば、一定の範囲で残業や休日労働を命じることができるようになります。ここで締結する労使協定のことを「36協定」といいます。
労使協定とは、会社と労働者との間で交わされる協定のことをいいますが、36協定も労使協定の1つです。
正式名称は「時間外・休日労働に関する協定届」ですが、労働基準法36条に基づいているため、「36協定」といわれています。
労使協定って何?
36協定は労使協定の中の1つです。そこで、まずは労使協定がどのようななものなのか解説します。
労使協定とは、会社と労働者との間で締結した書面による協定のことをいい、主に労働条件を対象に締結されます。
基本的に会社と労働者の労働条件については、労働基準法という法律がルールを定めており、違反すると処罰される可能性があります。
ですが、労働基準法には基本的な労働条件の規定しかないため、会社の実情に合わせたルール作りができません。
例えば、労働基準法では休日は1週間に1日以上必要とされていますが、企業によっては、忙しい時期にどうしても従業員に残業や休日出勤をしてもらいたいというケースもあるでしょう。
このとき、会社と労働者間で労使協定を締結すれば、労働基準法の規制が解除され、残業や休日出勤を命じても、労働基準法違反で罰則を受けることがなくなるのです。
法定労働時間や所定労働時間の意味
36協定は、労働者に対して、法定労働時間を超えて残業を命じることができるようになる労使協定です。
そこで、36協定を正しく理解するには、法定労働時間の意味や所定労働時間との違いについて、知っておくことが重要です。
まず、労働基準法では「会社は労働者に対して、1日8時間かつ1週間40時間を超えて労働をさせてはならない」と定められています。
この1日8時間、1週間40時間という労働時間の上限のことを法定労働時間といいます。法定労働時間に休憩時間は含まれません。
一方で、法定労働時間の範囲内で、会社が自由に決めることができる労働時間のことを、所定労働時間といいます。
例えば、会社の就業規則で労働時間は午前9時から午後5時まで(休憩1時間)と定められている場合、所定労働時間は7時間となり、1日の法定労働時間よりも1時間少ないということになります。
仮にこのケースで、2時間の残業が発生した場合、最初の1時間は法定労働時間の範囲内であるため割増賃金の支払いの必要はありませんが、後半の1時間については、法定時間外労働となるため、36協定の締結が必要で、かつ、割増賃金の支払い対象となります。
残業は原則禁止
労働基準法では、原則として、法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えた残業や休日労働を禁止しています。
「残業は原則として禁止されている」ということについて、驚く担当者の方もいるかもしれません。
ですが、長時間労働による労働者の健康被害などを防ぐため、法律ではそのように定められているのです。
ただ、会社の業務量は時期によって異なるため、繁忙期に残業や休日労働をいっさい禁止してしまうと、効率的な会社経営はできなくなってしまいます。
結果的には、労働者に対する不利益にもつながってしまいます。
そこで、本来禁止されている法定時間外労働と休日労働を可能にするための届出が、36協定なのです。
会社と、過半数労働組合または労働者代表者とが労使協定を締結することで、原則禁止されている残業や休日労働ができるようになるのです。
36協定の届出や手続きについて担当者が知っておくべきポイント

従業員がいる場合、どんな業種・規模の会社であっても、36協定と全く無縁というわけにはいきません。
今はまだ36協定を締結していないという会社であっても、近いうちに手続きが必要になる可能性があります。
そこで、36協定を締結し、行政官庁に届出をするうえで、会社の担当者が押さえておくべき手続きのポイントについて解説をしたいと思います。
36協定は誰と誰が締結する?
36協定を締結するには、会社と労働者の双方の合意が必要です。
ここで問題になるのが、会社は誰と36協定を締結すれば、労働者と合意したといえるのでしょうか。
この点について、労働基準法では次の2つの方法を規定しています。
- 労働者の過半数を代表する労働組合がある場合はその労働組合が代表となって36協定を締結する
- 上記のような労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する人を選出し、その人と会社との間で36協定を締結する
よほど大きな企業でもない限り、労働者の過半数で構成する労働組合はありません。
そのため、多くの会社は上記2の方法で36協定を締結することになるでしょう。
ただ、労働者であれば誰でも「労働者の過半数を代表する人」になれるというわけではないので、注意が必要です。
労働者代表というためには、次の2つの要件を満たすことが必要です。
- 管理監督者でないこと
- 民主的な手続きで選出されたこと
36協定届を作成するうえで非常に重要なポイントなので、それぞれについて、詳しく解説をしていきます。
管理監督者でないこと
管理監督者とは、「労働条件の決定やそのほか労務管理について経営者と一体的な地位にある人」のことをいい、管理監督者は会社の労働者代表になることはできません。
なぜなら、管理監督者は労働者よりも使用者としての立場に近く、労働者代表にふさわしくないからです。
ここで注意が必要なのが、社内で管理職とされている立場と、管理監督者は必ずしも一致しないということです。
例えば、社内の役職が工場長や店長などであったとしても、人事権や労務管理に関する裁量権がほとんどない場合、労基法上の管理監督者には当たらない可能性があります。
逆に、役職がついていなくても、経営に深く携わっている人の場合、管理監督者にあたる可能性があります。
民主的な手続きで選出されたこと
労働者代表は、「その事業場の労働者の過半数を代表する者」でなければなりません。
ここでいう労働者とは、正社員だけでなく、契約社員や臨時職員、パートやアルバイトなど名称を問わず、その事業場で働いている人全てを差します。
また、「過半数を代表する」というためには、投票や挙手など、民主的な手続きによって、選出されていることが必要です。
使用者が特定の労働者を指名したり、他の立候補者を辞退させるなど、使用者の意向によって選出された場合は、民主的な手続きによって選ばれたとはいえないため、労働者代表になることはできません。
労働者代表が、法令上の要件を満たしていない場合、36協定は無効であり、残業や休日労働を命じることも違法になってしまいます。
労働者代表を選出するときは、きちんと条件や手続きを調べた上で、適正に選出するようにしましょう。
36協定届を労基署へ提出
36協定は、労使間で合意しただけでは効果はありません。
「36協定届」という書類を作成し、事業場を管轄する労働基準監督署に提出しなければ効果はないのです。
36協定届は厚生労働省や労基署のホームページからダウンロードすることもできますし、管轄の労基署の窓口でもらうこともできます。
提出の方法については、労基署の窓口へ持参する方法、郵送する方法、電子申請の3つがあります。
持参する場合、窓口は平日の営業時間内しか受付していないので、事前に管轄の労基署の場所や営業時間などを確認しておきましょう。
電子申請は、デジタル庁が運営する行政ポータルサイト「e-Gov」を通じて、インターネットで申請を行います。
後述する通り、電子申請については、本社一括届出の要件が緩和されるというメリットがあります。
36協定届の押印廃止
以前は、36協定届を作成する際に、使用者(会社の代表者)の署名と押印が必要でした。
しかし、政府によるテレワーク・デジタル化の推進を背景に、労働基準法が改正され、2021年4月からは、36協定届の署名・押印が不要になりました。
これにより、企業は面倒な押印手続きを省略できるというメリットがあります。
ただし、36協定届が36協定書を兼ねる場合は注意が必要です。
法改正により押印が廃止されたのは、36協定届のみであり、36協定書については、改正前と変わらず押印は必要であるためです。
通常、36協定を締結するには、労使間で36協定書を作成し、その内容を36協定届に転記して提出します。
もっとも、36協定書と36協定届は内容がほぼ同じなので、36協定届の控えを36協定書として利用することが認められています。
36協定届が36協定書を兼ねる場合、36協定届についても押印は省略できません。
うっかり、押印を省略して提出しないよう注意しましょう。
残業等を命じるには契約上の根拠が必要
36協定は、「法定労働時間を超えて労働者を働かせてはならない」という労働基準法上の規制を解除するという効力を持つにとどまり、労働条件を設定する効果はありません。
そのため、実際に労働者に残業や休日労働を命じる場合には、雇用契約書や就業規則などによって、労働条件を新たに設定する必要があるのです。
例えば、就業規則に「会社は業務上必要な場合は、36協定及び法令の定める限度において、時間外または休日に労働を命じることができる」等の記載が必要です。
契約上の根拠がないまま、従業員に残業などを命じた場合、法令違反になってしまう可能性があるので注意しましょう。
36協定で決める内容
36協定では、労使間で以下6つの事項について定めなければなりません。
- 時間外労働・休日労働をさせる必要のある具体的事由
- 時間外労働・休日労働をさせる必要のある業務の種類
- 時間外労働・休日労働をさせる必要のある労働者の数
- 1日、1ヵ月、1年について延長することができる時間数
- 時間外労働と休日労働を合算した時間数が、1ヵ月100時間未満であり、かつ2~6ヵ月の平均のいずれも80時間を超えないこと
- 有効期間
ここで定めた内容を36協定届に記載し、管轄の労基署に提出をします。
36協定の有効期間について
36協定の有効期間について、法令上の決まりはありません。
ただ、36協定を締結する際は、1日、1ヵ月、1年について、それぞれ延長できる労働時間数を決めなければならないとされており、その関係上、1年より短い有効期間を設定することはできません。
また、厚労省からは「定期的に見直す必要があることから、有効期間は1年とするのが望ましい」という見解が出されています。
そのため、多くの会社では、36協定の有効期間を1年間と定めています。
36協定は事業場単位で締結する
36協定は、会社単位ではなく、事業場単位で締結し、労基署へ届出をしなければなりません。
そのため、1つの会社であっても、大阪と東京に別の事業場がある場合、それぞれの労基署で36協定の届出をしなければなりません。
ここでいう事業場とは「同じ場所で相関連する組織的な作業をできる場所のこと」のことをいいます。
そのため、同じ場所であっても、行われている業務内容が全く違う場合には、別の事業場と判断される可能性があるので注意しましょう。
例えば、同じ工場内であっても、マシンのオペレーターと、工場内に設置されている食堂の調理師では、業務内容が全く異なります。
そのためこの場合に、オペレーターと調理師に残業を命じる場合は、それぞれ別々に36協定を締結する必要があるのです。
電子申請の場合は本社一括届出が可能
36協定は、会社単位ではなく事業場単位で手続きをする必要があります。
そのため、全国各地に工場や店舗があるなど、事業場が多い企業では、36協定の手続きへの負担が膨大なものでした。
そこで法改正により、「1つの過半数労働組合と36協定を締結している企業」については、本社でまとめて複数の事業場の手続きを行うことができるようになりました。
これを「本社一括届出」といいます。
しかし、1つの過半数労働組合を有する企業は一部の大企業に限られており、ほとんどの企業では、本社一括届出を活用することができませんでした。
そこで、2021年4月に要件が緩和され、e-Gov電子申請で手続きをする場合に限り、事業所ごとの労働者代表が異なる場合でも、本社一括届出を利用することができるようになりました。
これにより、多くの企業で、事業場ごとの手続きをする必要がなくなったので、大幅に手続きの効率化を図ることが可能になりました。
36協定による残業時間の上限
36協定を締結したからといって、何時間でも労働者に残業をさせてよいというわけではありません。
36協定では、1日・1ヵ月・1年あたりの時間外労働の上限を定める必要があり、通常の36協定だけでは1ヵ月45時間、1年360時間を超えて残業等を命じることはできません。
違反に対しては、罰則も設けられているので、36協定を締結する際は、上限についてしっかり確認しておくようにしましょう。
上限を超える場合は特別条項が必要
36協定にも上限が定められており、原則として1ヵ月45時間、1年360時間という上限を超えて時間外労働をさせることはできません。
ただ、会社によっては、業務量が大きく変動するため、通常の36協定の範囲内では対応できないという可能性があります。
そこで、労働基準法では、「臨時的な特別の事情」がある場合に限り、労使間の合意に基づき1ヵ月において労働時間の上限を延長させることができると定められました。
これを、特別条項付き36協定といいます。
特別条項を設けた場合、36協定で定めた時間外労働をさらに延長させることが可能になりますが、下記のルールを守らなければなりません。
- 1年間の時間外労働が720時間以内であること
- 時間外労働と休日労働の合計が1ヵ月100時間未満であること
- 時間外労働と休日労働の合計について、2~6ヵ月平均が1ヵ月あたり80時間以内であること
- 時間外労働が1ヵ月45時間を超えることができるのは1年間に6ヵ月まで
1ヵ月の時間外労働と休日労働の合計については、「100時間未満」とされているため、100時間と設定することはできず、「99時間」が上限となるので注意しましょう。
割増賃金の支払い
36協定を締結すれば、法定労働時間を超えて労働を命じることができるようになりますが、その場合、会社は労働者に対して割増賃金を支払わなければなりません。
割増率については、時間外労働については25%以上、休日労働については35%以上 、深夜労働(午後10時から午前5時まで)は25%以上 となっています。
時間外労働と深夜労働が重複した場合や、休日労働と深夜労働が重複した場合、割増率は合算されます。
そのため、時間外労働と深夜労働が重複した場合は50%以上、休日労働と深夜労働が重複した場合は60%の割増賃金を支払わなければなりません。
なお、休日に8時間を超えて残業をした場合、割増率の合算は行われず、35%の割増率のみが適用されることになります。
月60時間を超える場合の割増賃金に注意
長時間労働の問題が深刻化する中、労働基準法が改正され、一定の基準を満たす大企業については、時間外労働が月に60時間を超える部分について、割増率が25%以上から50%以上に引き上げられました。
そのため、例えば月の時間外労働が80時間であった場合、60時間までは25%、60時間から80時間までは50%で計算をします。
この60時間を超えた部分については、事業場の過半数代表者と労使協定を締結することにより、有給の代替休暇を与えることを定め、割増賃金の支払いに代えるという対応も認められています。
現在、この割増率が適用されるのは、一定規模以上の大企業のみですが、2023年4月からそれ以下の中小企業も適用範囲に含まれます。
急な割増賃金の増加など、中小企業にとって大きな負担となる可能性がありますので、なるべく早めに対応を進めるようにしましょう。
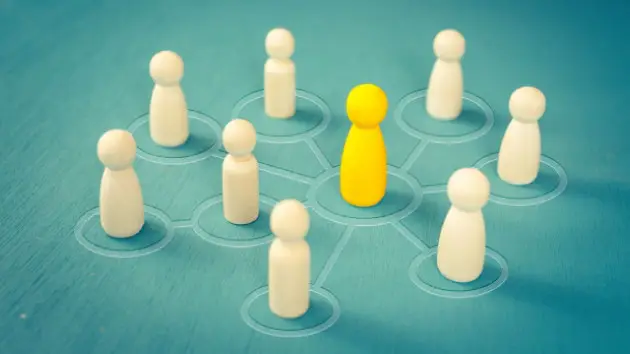
まとめ
法律上、残業や休日労働は原則として禁止されており、会社が労働者にこれを命じるためには、36協定を締結する必要があります。
36協定とは「時間外・休日労働に関する協定届」のことをいい、事業場単位で締結し、管轄の労基署に提出することが必要です。
36協定を締結する場合、労働者代表の選出や、割増賃金の支払いなど、会社として検討しなければならないことがたくさんあります。
そのため、36協定を締結しようとする場合、担当者はしっかりと内容を理解し、早めに社内で対応するようにしましょう。
36協定について、ご質問やご相談のある方は、ぜひSATO社労士法人にお問合せください。
全国最大手の社労士事務所ならではのノウハウで、お客様の課題解決を全力でサポートいたします。










