
36協定を締結すると残業時間の上限はどうなる?

社が労働者に対して、残業や休日労働を命じるには、労使間で「36協定」を締結し、管轄の労基署に届け出しなければなりません。
ただ、36協定を締結したからといって、無制限に残業や休日労働を命じることができるようになるわけではありません。
では、36協定を締結すると残業時間の上限はどうなるのでしょうか。
今回は、36協定を締結した場合の残業時間の上限や、手続きの注意点などについて解説したいと思います。
”「最新の法改正」や「人事トレンド」など、人事・労務担当者必見の資料を配布中!”
→こちらから無料でダウンロードできます
そもそも36協定の意味って何?

36協定とは、簡単に言うと従業員の残業や休日労働に関する協定のことをいいます。
そもそも労働基準法では、「1日8時間・1週間40時間以上」労働者を働かせてはならないとされており、原則として残業や休日労働は認められていません。
この「1日8時間・1週間40時間」という制限のことを、法定労働時間といいます。
つまり事業者は、原則として法定労働時間を超えて労働者を働かせることができないのです。
しかし、残業や休日労働が一切認められないと、会社は急な業務量の増減に対応することができず、効率的な運営ができなくなってしまいます。
そこで、労使間で協定を締結し届出をすれば、例外的に、労働者に残業や休日労働をさせることができるようになるのです。
このとき締結する協定が、労働基準法36条に基づいているため、「36協定」といわれています。
36協定の締結で残業時間が「月45時間」「年360時間」まで可能
では、会社が36協定を締結するとどうなるのでしょうか。
36協定を締結した事業所では、法定労働時間を超えて労働者を働かせることが可能になります。
ただし、何時間でも働かせてよいということでは、もちろんありません。
36協定を締結した場合の上限は、原則として1ヵ月45時間、年間360時間までの残業・休日労働とされています。
ただし、対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制を導入している事業所の場合、1ヵ月42時間、1年間320時間が上限となるので注意しましょう。
36協定は労基署への届出が必要です
36協定は締結後、管轄の労働基準監督署に届出をしなければ効果が生じません。
たまに、「36協定を労使間で締結すれば残業を命じることができる」と、勘違いして、届出を忘れている担当者の方がいるので注意しましょう。
また、36協定は1度締結すれば、ずっと有効というものではありません。
36協定には有効期間があり、期間ごとに管轄の労基署へ届出をしなければなりません。
基本的に有効期間を1年間としている会社が多いので、その場合、労働者に残業を命じるためには毎年届出をする必要があります。
残業や休日労働が発生する会社の担当者は、自社の36協定の有効期限が切れていないか確認し、期限内に手続きをするようにしましょう。
36協定を締結せずに残業をさせることは違法
36協定を締結しないと、会社は労働者に残業をさせることができません。
では、36協定を締結しないまま、労働者に残業をさせるとどうなってしまうのでしょうか。
会社が36協定を締結せずに、労働者に残業をさせたり、または、休日に労働させた場合、労働基準法違反として処罰される可能性があります。
このときの罰則は、「6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金」です。
罰則を受けるのは、残業や休日労働をした労働者ではなく、会社の代表者や、残業を命じた管理者です。
また、場合によっては、労働基準監督署によって違法な残業等があったとして、社名が公表されることもあります。
社名が公表されると、法令違反を犯した企業として、企業イメージの悪化・信用の低下につながります。
従業員に残業や、休日労働を命じるときは、必ず36協定を締結しているかどうか、有効期限は切れていないかどうか、確認するようにしましょう。
特別条項付36協定でさらに延長が可能
ここまで説明したとおり、36協定を締結して届出をすると、労働者に対して月45時間、年間360時間までの残業・休日労働を命じることが可能になります。
ただ、会社の業務量は、状況によって大きく変化するため、場合によっては月45時間、年間360時間という上限では足りないという状況が発生するかもしれません。
そこで、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加が予想される場合」に限り、特別条項を36協定に付けることで、上限を超えて、労働者に残業や休日労働を命じることができるようになります。
これを、「特別条項付き36協定」といいます。
特別条項付き36協定を締結すると、月100時間未満、年間720時間、複数月平均80時間以内まで法定時間外労働の上限を延長することができます。
ただし、あくまで例外的な措置となるため、上限を延長できる月は、1年間に6回までとなります。
また、特別条項付き36協定の届出をする際は、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加が予想される場合」をできる限り具体的に定めなければなりません。
「業務の都合上必要な場合」など、抽象的な定め方では受付をしてもらえない可能性があるので注意しましょう。
36協定を締結し届出をするまでの流れ

通常、36協定は次の流れで締結・届出を行います。
- 労働者代表を選出
- 36協定書(36協定届)を作成
- 労働者への周知
それぞれについて、解説します。
労働者代表を選出する
36協定の締結は、従業員の過半数で組織する労働組合(過半数組合)がある場合は、会社とその労働組合が行います。
ここでいう従業員とは、正社員だけでなく、パート・アルバイトなど、名称を問わずその事業場で働くすべての労働者が含まれます。
36協定を締結する際は、その事業場で働く労働者の数と、労働組合に加入している労働者の数をあらためて確認するようにしましょう。
過半数組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者(労働者代表)と、36協定を締結します。
過半数代表は、労働者であれば誰でもよいというわけではなく、次の2つの要件を満たしていていることが必要です。
- 管理監督者にあたらないこと
- 投票や挙手、話し合いなど民主的な手続きによって選出されたこと
管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある人のことをいいます。
また、民主的な手続きというためには、パートやアルバイトなど全ての労働者が手続きに参加できるようにすることが必要です。
36協定書(36協定届)を作成
事業場ごとに、使用者と過半数組合、又は労働者代表が協議して、36協定を締結します。
このとき、労使間で作成する書類のことを「36協定書」、労働基準監督署に提出する書類を「36協定届」といい、この2つは別の書類です。
しかし、「36協定書」と「36協定届」の内容はほとんど同じものであるため、通常は、36協定届を2部作成し、これを管轄の労基署に提出し、控えの1部を36協定書として保管をします。
なお、令和3年4月から、労働基準法の改正により、それまで必要だった36協定届の署名・押印が不要になりました。
しかし、署名・押印が不要になったのは、「36協定届」のみであり、「36協定書」については、署名・押印は必要です。
そのため、上記のように「36協定届」の控えを「36協定書」として使用する場合には、署名・押印の省略はできない点に注意が必要です。
労働者への周知
会社は36協定を締結したら、その内容を事業場で働く労働者に対して広く知らせなければなりません。
これを36協定の「周知義務」といいます。
36協定の周知方法には法令でルールが定められており、次のいずれかで行わなければなりません。
- 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
- 書面を労働者に交付すること。
- 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
事業場で働く労働者が見ようと思えばいつでも見える状態にあることが必要となるため、鍵のかかったキャビネットの中にしまってある場合や、管理者しか入れない部屋に掲示してある場合等は、周知義務を果たしているとはいえません。
周知義務違反に対しては、労基法違反として30万円以下の罰金が科される可能性があります。
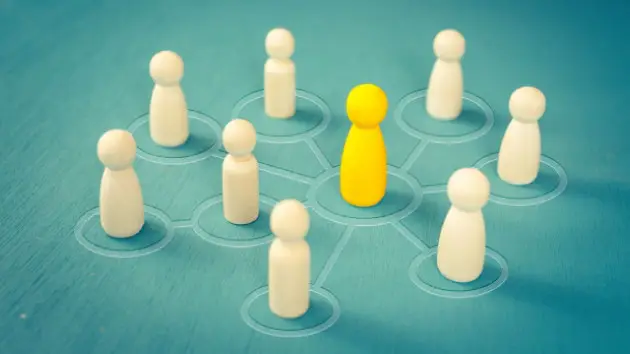
まとめ
36協定を締結し管轄の労基署に届出をすると、残業時間の上限は「月45時間・年360時間」となります。
また、場合によっては特別条項付き36協定を締結することで、「月100時間未満」「年720時間以内」「複数月平均80時間以内」まで上限を延長することが可能です。
ただし、特別条項付き36協定を締結するには、「通常予見することのできない業務量の大幅な増加が予想される場合」でなければなりません。
36協定を締結することなく、従業員に残業や休日労働をさせると、労基法違反として処罰される可能性があります。
残業が発生する場合は、36協定が締結されているかどうか、36協定の有効期限が切れていないかどうかなど、事前に確認するようにしましょう。










